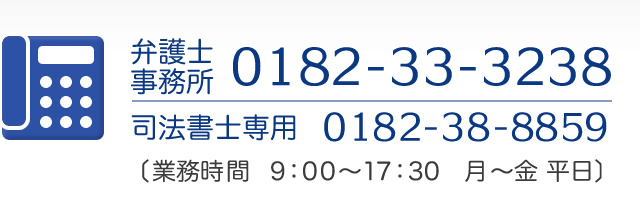平成14年(ワ)第20642号,23679号,24245号,平成15年(ワ)第1738号各不当利得返還請求事件
最高裁HP,判例時報1846号29頁
裁判官 齋藤隆,小川直人,鈴木敦士
控訴審 H17.02.24東京高裁判決(2)
上告審 H18.11.27最高裁判決(2)
【事案の概要】
大学合格後,入学を辞退した受験生が,前納した入学金及び授業料等の返還を求めた。
【判断の内容】
① 在学契約について,準委任契約又は同契約に類似した無名契約ではなく,教育法の原理及び理念により規律されることが予定された継続的な有償双務契約としての性質を有する私法上の無名契約であるとした。
② 入学辞退について,民法651条1項の適用ないし類推適用を否定しつつ,受験生側からの自由な解除を認めた。
③ 入学金について,入学手続上の諸費用に充てられるほか,在学契約上の地位の取得についての対価として,返還義務を否定した。
④ 大学が2条2項の「法人」にあたるかについて,情報の質及び量並びに交渉力に格差のある大量的契約の当事者については公益性を問うことなく規制の対象とするのが同法の趣旨であると指摘し,法人に含まれるとした。
⑤ 「平均的な損害の額」(9条1号)の立証責任は事業者側にあるとした。
⑥ 授業料を返還しないとの特約について,4月1日より前に入学を辞退した者について,9条1号により無効であるとして返還を命じた。4月1日以降の入学辞退者については,授業料の返還を否定した。