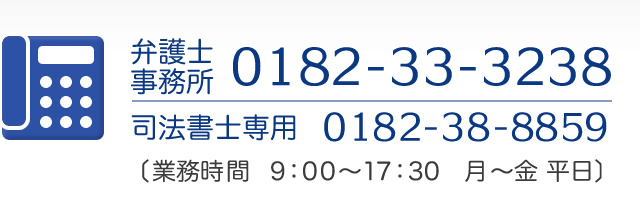平成16年(ハ)第4044号立替金請求事件
最高裁HP
裁判官 野中利次
【事案の概要】
訪問販売で日本語をよく話せない中国人に教材を売りつけた事案で,信販会社が立替金を請求した。
【判断の内容】
①販売店の担当者がクレジットの返済月額を1万2000円位であると説明したが,実際にはその倍以上の引き落としであったこと等について不実告知と認め, 本件クレジット契約は信販会社が販売店に媒介を委託したものであるとして(5条),4条1項による取消しを認めた。②騙されたことを知った後に立替金を支 払っていたとしても,相手方に対して追認の意思表示がなされた訳ではないとして,追認の主張を排斥しクレジット契約の取消しを認めた。